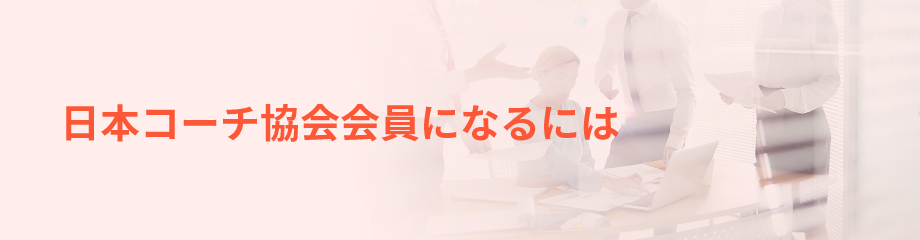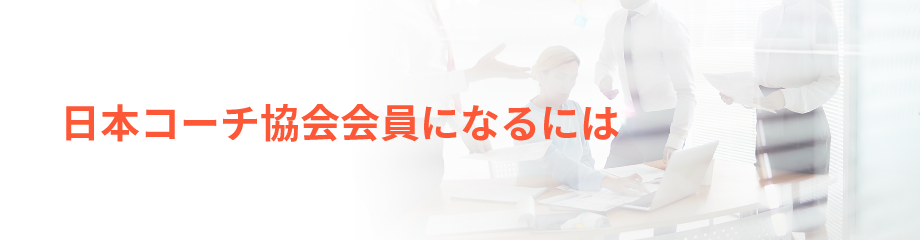最近、職場にいるとき、クライアントとセッションしているとき、営業場面でも、
ある問いが私の中に浮かんでいることに気づきました。
「この人にとって、上司・同僚・部下は“機能”だろうか? それとも“人間”だろうか?」
実際にこの問いをクライアントに投げかけると、沈黙が訪れることもしばしばあります。
「もちろん、人として接している」と答える方もいらっしゃいますが、「その言葉の奥
には、人は、事業目的を達成するための“機能”であるという前提がないだろうか?」と思う
のです。
かくいう私自身、「この人は使える」という視点で人を見ていたり、「この上司について
いけば出世できる」と当然のように思ってきたと振り返って思います。
しかし、そんなこれまでの自分に「ハッ」と気づかされた出来事がありました。
それは、ある企業の組織変革プロジェクトのキックオフでした。参加者の一人が、
不満げにこう言ったのです。
「上司との関係って、利害関係以外に何があるんですか?」
ファシリテーターをしていた私は、その方の言葉に、胸がつまりました。
その後よくよく考えると、コーチングプロジェクトをオーナーや事務局の方と一緒に
設計していると、こんなやり取りが実際に起こることを思い出しました。
「経営チームの信頼関係を強化したい理由は?」
「其々の部門利益を超えた議論をしたい」
「部下と信頼関係をつくる理由は?」
「そのほうが成果につながるから」
「チーム内で対話を推奨する理由は?」
「そのほうが心理的安全性が高まり、生産性が上がるから」
たしかに、チーム内の信頼は成果に寄与する、と言われます。
ただ「信頼さえも、成果のための“手段”と化していて、本当に期待通りの成果に
つながるのだろうか?」という疑問もわくのです。
成果主義、KPI、役割定義、報酬制度。
いずれも目的合理性の上に組み上げられたシステムです。
そのこと自体が悪いわけではありませんが、職場の人間関係が“機能”を重視して
構築されるとき、関係性は業務上都合のよい限りでしか扱われません。
やがて「この人は使える」「あの人は空気が読めない」「あの部署は非協力的だ」と
いった言葉が組織内に静かに浸透していき、人が役割や生産性で分類される風土が
形成されていきます。
しかし、誰でも職場を出れば、誰かの親・子供・妻・夫であり、誰かのかけがえのない
友人や仲間です。また、一人ひとりに感情があり、それぞれが大事にしていることもあります。
それなのに職場に入ったとたん、それらを抑えて“機能”としてのみ振る舞うことで、
私たちは誠実な対話の機会を失い、どれだけの創造性を失ってきたのでしょうか。
”強い”組織をつくるために
「社員の心に火をつける」という組織変革プロジェクトに参加している、Aさんのお話です。
彼は5つの部門を束ねるリーダーたちの「心に火をつける」ための対話を重ねていました。
しかし、どうも思うようにいかないことに、焦りを感じていました。
「Aさんのお話を聞いていると、焦っている気持ちと同時に、彼らへの遠慮を感じます。
これはどこから来るんでしょう?」
「……」
「それでは問いを変えていいですか。Aさんは、お子さんの教育方針には、どのような
一家言をお持ちですか?」
「うちは、娘が小さいころから、娘の欲求通りにならなくて泣いても
『泣いてるだけじゃ、だめだよ。なぜそれが欲しいのか、ちゃんと考えて、僕たちを
説得しなさい』と言ってきました。今、娘は中学生になりましたが、毎週末、高等裁判所の
裁判を傍聴しにいく、面白い子になりました」
Aさんは、照れくさそうにそう話してくれたあと、短い沈黙が訪れました。
そして、ふっと気づいたように、おっしゃいました。
「自分は、今の部下たちの成長に本気で向き合ってなかったのかもしれないね」
経営において“機能性”は必要です。組織は目的を持つ集団であり、効率や成果から完全に
目を背けるわけにはいかないでしょう。ただ、人を“機能”として“だけ”扱うとき、信頼は
生まれず、創造は起こらないのではないでしょうか?
長期的に継続して成果を生む組織は「人を“人”として見る文化」を育てているのでは
ないでしょうか。その文化が育まれている組織では、「調子どう?」という何気ない
問いかけの中に、その人への関心があります。また、相手の背景に敬意を払いながらも、
言いにくいことをあえて伝えられる関係性や会話があります。
そのような組織では、心理的安全性が醸成され、意見の多様性が活かされ、挑戦と対話が
自然に生まれていきます。そして数字だけでは測れない、けれども、創造性にあふれた
“強い”組織が育っていくのです。
問いを戻しましょう。
あなたにとって、職場の人間は“機能”ですか? “人”ですか?
私たちにとって、上司・同僚・部下は、どんな存在ですか?
この問いに正解はありませんが、同じ職場の仲間同士で対話することこそ「人を“人”として
見る文化」を育み、”強い組織”をつくっていく力が宿ると信じています。
日本コーチ協会 正会員
田邉 曜子
コーチングニュース Vol.277
2025年07月25日