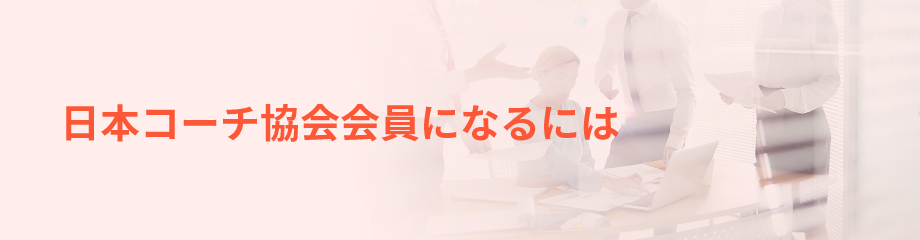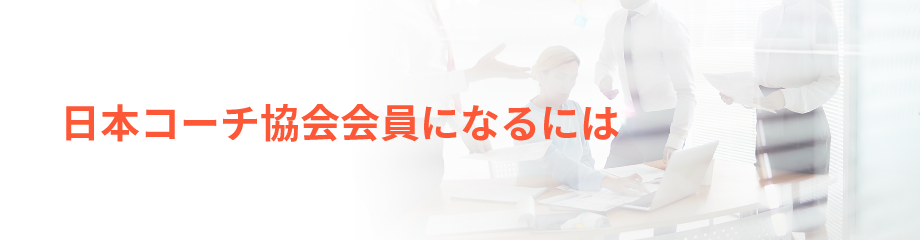この数年、様々な企業の経営層の方々から「変革リーダーが不足している」という話を
聞くことが多くなりました。
多少の違いはあれど、彼らが危惧していることは共通しているように思います。
それは「ビジネス環境が大きく変化する中で、これまでの延長線ではない未来を描き、
周囲を巻き込み、変化を起こせるリーダーの存在がもっと必要だ」ということです。
私がコーチをしているクライアントの多くは、部下をもつ方々です。
彼らに「あなたは何を実現したいのですか?」と問うと、多くの方が「主体的な部下を育てたい」
「部下がもっと自由な発想をできるようになって欲しい」と答えます。
私自身も管理職として、メンバーの主体性を高めることが自分自身の役割だと認識しているので、
このこと自体を否定するつもりはありません。
しかし、リーダーが周囲の主体性を高めるだけで、これまでの延長線ではない未来に
つながるのでしょうか?
彼らの話を聞くたびに私の中には違和感が生まれました。
そして次第に、部下の主体性を高めるリーダーと、冒頭に紹介した経営層の方々が言う
「変革リーダー」は異なるのではないかという問いが、頭の片隅に居座るようになりました。
あなたがやりたいことは何ですか?
昨年、私のこの問いに一つの答えをくれた体験がありました。
ある製造業のプロジェクトにコーチとして参加したときのことです。
そのプロジェクトは本部トップの「次世代を担う部長層に、部門・会社経営の一端を
担えるリーダーになって欲しい」という想いからスタートしたものでした。
次世代リーダーとして、私が担当することになったのは開発部門の部長Aさん。
とても温和でバランスがよく、部下や同僚から信頼されている方でした。
Aさんはコーチングで「リーダーとして部門のみんなに指し示す魅力的なビジョンを描きたい」
をテーマにしていたので、「魅力的なビジョンというのはどういうものなのか」を探索すること
からはじめました。
しかしいざ「Aさん自身は会社で何を実現したいのですか?」とAさんのビジョンを聞いてみると、
出てくるのは開発部門メンバーへの期待やメンバーに変化して欲しいこと、また、世の中のニーズの
変化に対応しなければいけないという話ばかりで、Aさん自身が実現したいことは出てきません。
私はAさんの話は理解出来るものの、聞いていてワクワクしませんでした。
ビジョンとは想いである
Aさん自身からはなぜビジョンが出てこないのだろう? と思いつつ、Aさん自身が、リーダーの
ビジョンに影響を受けた体験があるかどうかを聞いてみたところ、上司のビジョンがAさんの
思考の枠を広げ、Aさん自身の主体性にも働きかけた体験があることがわかりました。
しかし実は、最初にその上司のビジョンを聞いたとき、「さすがにこれは無理だろう」と思った
といいます。
「正直、最初は驚きや否定の感情が沸き上がってきました。でも、上司からビジョンへの熱い想いが
伝わってきて、実現にむけて何ができるかを考えるようになっていたんです」
ビジョンとは、時に無理難題であっても「とにかくこれを目指そう、一緒にやろう」という強い
信念とともに発信するものではないか。その想いこそが、ビジョンを魅力的にするのではないか。
そのことに気づいたAさんに改めて「何を実現したいのか?」と問いかけてみると、少し間をおいて
こう言いました。
「管理職の仕事は経営と部下を繋ぐことで、自分がどうしたい、というのは言うべきではないと
考えてきました。だから自分が何をしたいのかよりも、周囲から求められていることは何か、
世間が面白いと思うことは何かというように、自分の外側のことを考えてしまうんです」
役割への認識が変わると、思考も変わる
リーダーとして部門のみんなに指し示す魅力的なビジョンを描きたい、という思いがあるのに
それが出てこない。
私はAさんの「管理職」という役割への認識が、魅力的なビジョンを描きにくくさせて
いることに気づきました。
そこから管理職・部長という役割を脇に置いて、「自分がやりたいことは何か?」という
Aさん自身を主語にした問いでコーチングを進めました。
・Aさんは開発の仕事の何が楽しいのか?
・Aさんは自社製品の何が好きなのか?
・Aさんがユーザーとして面白そうだと思うものは何か?
・Aさんは周囲とともにどんな体験をしたいのか?
やりたいことがだんだんと明確になってきたときに、Aさんは言いました。
「リーダーだからこそやりたいことを言わないと、部下のやりたいことも引き出せない。
間違えていたとしても、はっきりとしたビジョンを指し示していかないと今までの
延長戦ではない未来は作れない」
周囲と対話をして未来を共に描いて作っていく
このプロセスで、Aさんの管理職に対する役割認識は「上と下を繋ぐ」ではなく、
「自らが未来を描きながら、周囲と共に未来を作る」と変化していきました。
そして描いた未来を実現するために、他部門や同僚・上司・部下に自分のビジョンを伝えた
うえで対話をする機会を持ったり、部下に仕事を任せる幅を広げるなど、自ら変化を起こし
始めました。
また、開発部門の組織構成についても、これまでとは異なる前提で考え直す必要があると、
周囲を巻き込んで議論を始めているそうです。
変革リーダーというのは、「部下を主体的にさせよう」とするだけではなく、その人自身が
未来を創る主体者として自らのビジョンを表現し、周囲を対話に巻き込むことが出来る人です。
リーダー自身の責任で発信されるビジョンが、結果的に部下の思考の枠を広げ、思考や行動に
影響し、部下の主体性を高めるのだと思います。
本当にやりたいことはなんですか?
こう聞かれたとき、その答えは簡単には出てこないかもしれません。
しかし、その問いに向き合うことが、変革リーダーとなる第一歩なのかもしれません。
日本コーチ協会 正会員
酒井春奈
コーチングニュース Vol.275
2025年06月03日